餅つき

今年も年の瀬が迫ってきた。
子供の頃、年末になると、両親がいつも餅つきをしてくれていた。
母が庭先に即席のおくどさんみたいなのを作って四角いせいろを何段か積み重ねてもち米を蒸していた。
そのもち米を蒸している匂いがとても好きだった。
父は大きな石臼を出してきて、お湯で石臼を洗って餅つきの準備をして、私は始まるのをワクワクして待っていたのを思い出す。
餅つきが始まると、餅つきの杵(きね)を大きく振りかざして餅を突く父の姿がとてもかっこよく思った。
1回ごとに餅がつき上がると、母が餅を適度な大きさに手でちぎり、それを姉とふたりで手で餅を丸く整える。結構忙しかった。私がやると、シワができたりしてへたくそだったように思う、たまに上手くできると姉や母に自慢したのを思い出す。それを「もろぶた」と言う餅箱にきれいに並べるのも、子供の役割だった。
せいろひとつ分は必ずあんこ餅、つきたてのあんこ餅を食べるのが嬉しかった。
一番最後に鏡餅を作るのは父の役割だった。その姿もやっぱりかっこよかった。
子供の頃は、当たり前のように毎年過ごしていたのが、とても懐かしい。
いつの頃からか、電気餅つき機が家にやってきて、せいろで餅米を蒸したり、石臼で餅をついたりがなくなり、いつの間にか餅つきそのものもやらなくなって、既製品になってしまった。
便利さの代わりに、何かがなくなったような気がするのは私だけだろうか。



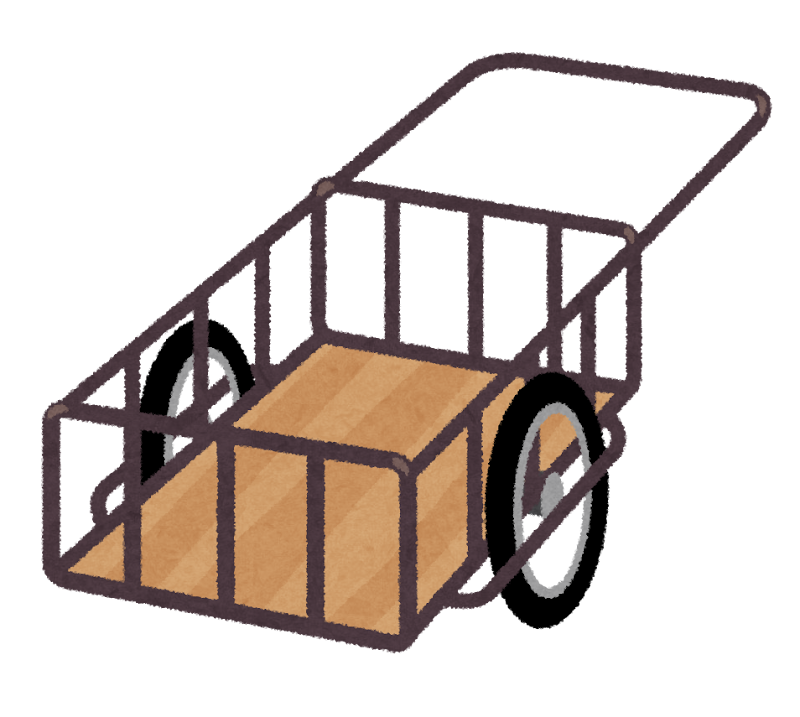



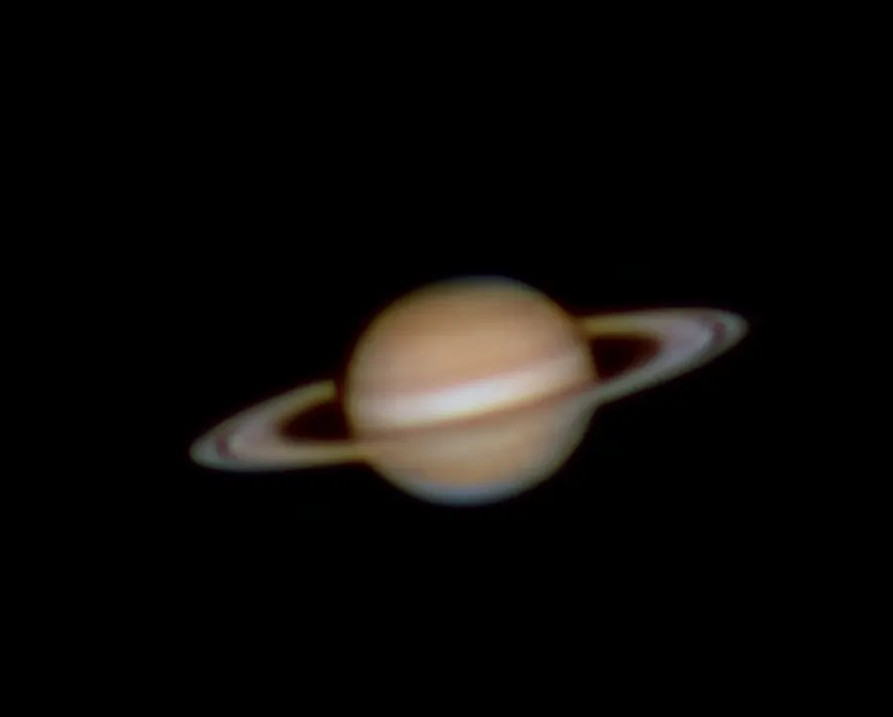

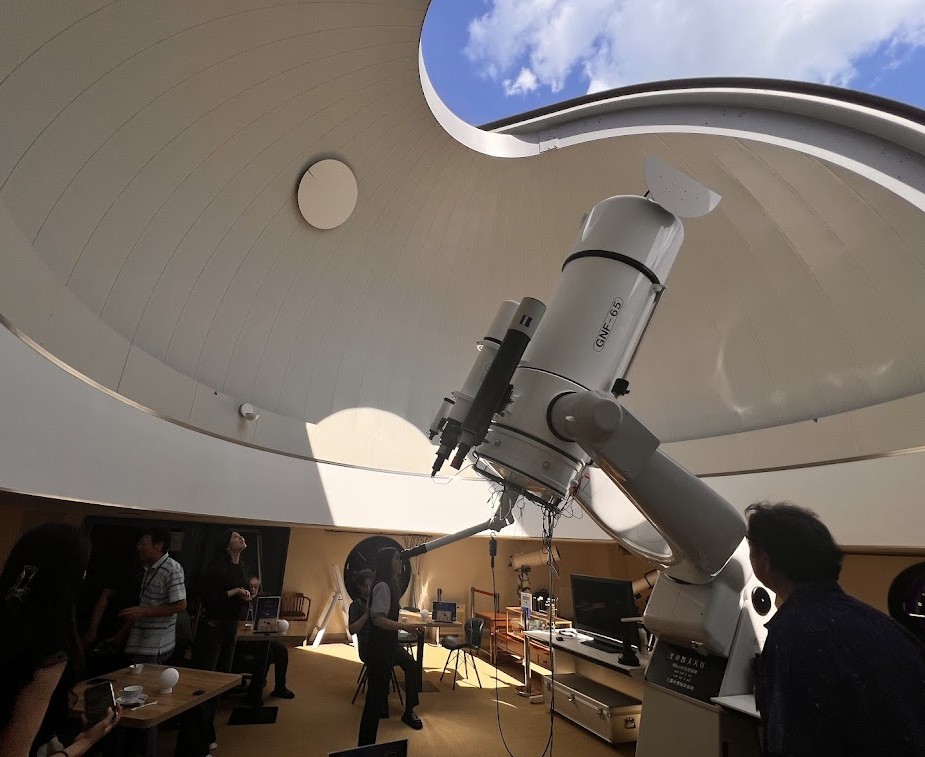

コメントを残す